- 文化情報
2023.06.02
振袖の柄、どんな意味?

20歳の式典での楽しみといえば
華やかな振袖姿、という方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな華やかな振袖の柄に込められた
様々な意味をご紹介♪
これから振袖を選ぶ方も、柄の意味を知って
振袖選びに活かしてくださいね。
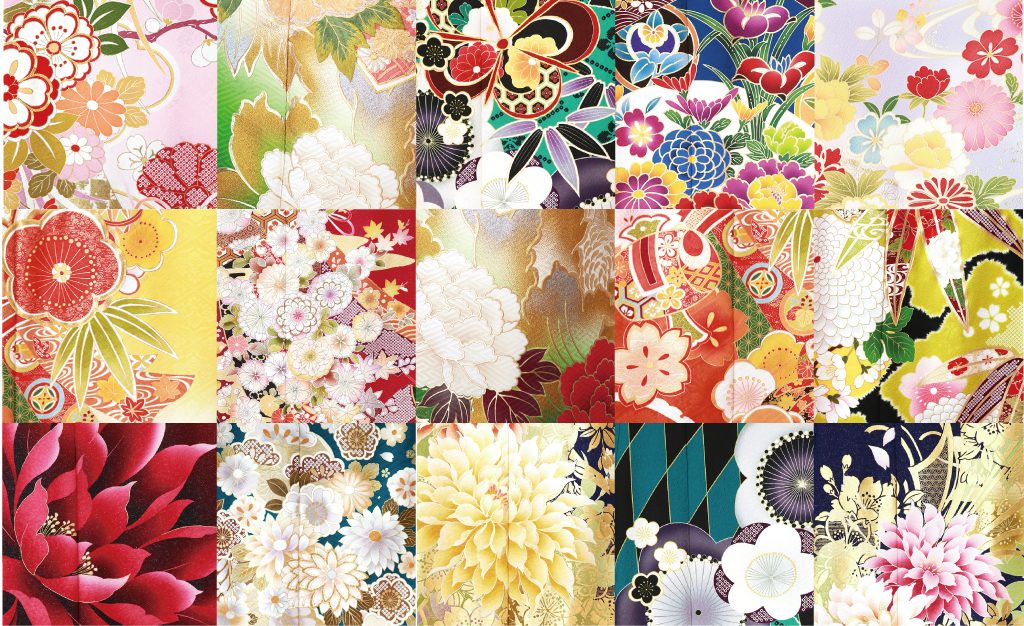
ーーーーーーーーーーーーー
花柄
◆桜(さくら)
桜は昔から日本人に愛されてきた花で、古くから着物の柄にも多く使われてきました。
桜の季節である春は、芽吹きの季節。そのため物事の始まりに縁起が良いとされる柄です。
また、五穀豊穣の意味もあるため、繁栄するようにという願いも込められた柄です。
◆菊(きく)
菊の花は日本のパスポートや皇室の門にも使われている国民的なモチーフです。
菊には薬効があるため中国では”仙花”と呼ばれていて、日本にも薬草として伝わったそうです。
そのため菊の柄には「長寿」や「無病息災」といった意味が込められています。
◆梅(うめ)
厳しい冬に耐えて咲く梅は、「忍耐」、「困難に耐える」という意味を持ちます。
また、うめを「産め」に掛けて、「子孫繁栄」の願いが込められた柄でもあります。
◆牡丹(ぼたん)
牡丹の花は豪華に咲くその姿から「百花の王」とも呼ばれています。
昔から「富貴(金持ちで地位や身分が高いこと)の象徴」として用いられてきました。
その他に「美しさ」という意味も持った柄です。
◆椿(つばき)
椿は冬でも葉を落とさないため、古くから魔除けの力を持つ木と考えられてきました。
そこから、「厄除け」の意味を持つ柄として使われています。
その他に「高貴」といった意味も含まれています。
ーーーーーーーーーーーーー
身の回りの道具の柄
◆扇面(せんめん)
扇は末広がりの形から、縁起が良いものとされていて、
「開運」や「繁栄」を表しています。
「未来の展望が明るい」という意味を持つ縁起の良い柄です。
◆宝尽くし(たからづくし)
打出の小槌や巾着、宝巻、隠れ蓑、隠れ笠、宝珠…などが描かれた宝尽くし。
中国の仏教の宝の文様である「八宝(はっぽう)」を日本に合うように変化させた文様です。
「開運招福」の意味が込められた、おめでたい柄です。
◆熨斗文(のしもん)
お祝いの時に送るものに添えられる熨斗をモチーフにした柄です。
熨斗を使う場面から、おめでたい意味を持った柄として使われています。
◆手毬(てまり)
手毬はその形から、「何事もまるく収まるように」や、
「家庭円満」といった願いを込められた柄です。
ーーーーーーーーーーーーー
生き物の柄
◆鶴(つる)
鶴の柄はおめでたい文様として、「長寿」の意味を込めて用いられてきました。
また、鶴の鳴き声がよく通ることから、
声が天までとどくありがたい鳥という意味合いもあります。
◆蝶(ちょう)
蝶は あおむし から さなぎ、成虫へと変化することから、
「立身出世」「不死」といった意味が込められた柄です。
ーーーーーーーーーーーーー
いかがでしたか?
振袖にはその他にも様々な柄があります。
ご自分でも気になる柄の意味を調べてみると
振袖選びがもっと楽しくなりそうですね♪
〜スズヤグループの公式サイトはこちら〜
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
〜MEMORIES OF LIFE〜
メディアサイト「MOL」を運営している株式会社鈴屋は
みなさんが人生の節目の瞬間をより素敵に彩り、より幸せを実感でききますよう応援しています。






